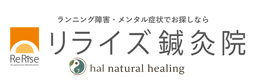アキレス腱炎は、ランナーに限らずジャンプ動作や歩行を繰り返すスポーツ全般で発生しやすい代表的な障害のひとつです。
「ふくらはぎの下あたりが重だるい」「朝起きて一歩目にズキッと痛む」「走り始めは痛いが、温まると少し楽になる」――そんな訴えで来院される方が多く見られます。
一見、単純な“使いすぎ”の炎症のように思われがちですが、背景には足首・膝・股関節・骨盤など全身の連動の乱れが関与していることが多く、局所のケアだけでは再発を防ぎきれません。
今回はアキレス腱炎の病態理解と、再発を防ぐためのコンディショニングの考え方について解説します。
病態とメカニズムの理解
アキレス腱炎は、下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)の収縮ストレスがアキレス腱部に過度に集中し、微細損傷や炎症が起こる障害です。
主にアキレス腱下部(踵骨付着部近く)、または腱中央部(ミッドポーション)に発生します。
炎症の直接的な原因は「過剰な牽引・繰り返しの伸張負荷」ですが、そこに至る背景にはいくつかの共通パターンが見られます。
●足首(距腿関節)の背屈制限
●下腿三頭筋(特にヒラメ筋)の過緊張
●骨盤の前傾や股関節伸展制限による代償的な足部のオーバーワーク
●オーバーストライド(接地位置が前方すぎる)による衝撃集中
●シューズの摩耗や接地面の硬さの影響
◆これらが重なることで、アキレス腱に「引っ張られ続ける環境」が生まれ、炎症が慢性化していきます。とくにランニング動作においては、足関節背屈可動域の低下とふくらはぎの張りがセットで存在していることが多く、これが「常に腱が伸ばされている状態」を作ります。
アキレス腱痛のコンディショニング
初期段階では、炎症部位の鎮静化、損傷部の治癒促進を最優先に行います。
具体的には、超音波療法・ハイボルト・鍼灸・冷却などを発生からの期間や発痛度合い、状態にあわせて使い分けます。
次に重要なのは、ふくらはぎ周囲筋群(腓腹筋・ヒラメ筋)の柔軟性回復と下腿~足部のアライメント改善です。
硬くなった筋肉を単に「伸ばす」だけでなく、収縮と伸張のバランスを取り戻すことが鍵になります。
以下の点を意識してコンディショニングを進めます。
●ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)のリリース・ストレッチ
●足底筋膜や足趾屈筋群の柔軟性向上
●足関節背屈可動域の改善(特にヒラメ筋制限への対応)
●片脚バランスやカーフレイズによる機能的再教育
●骨盤・股関節の伸展動作を取り戻すエクササイズ
◆痛みが落ち着いても、腱の再構築(コラーゲン線維の再配列)には時間がかかるため、完全な回復には数週間~数ヶ月を要することがあります。
焦らず、「痛みが取れた=治った」ではないことを理解しておくことが大切です。

《アキレス腱炎のコンディショニングポイント》
●足首(距腿関節)の背屈制限
● 骨盤・股関節の可動性回復
●重心位置(体幹のアライメント)の調整
●ランニングフォームの見直し
上記にポイントを充てなければ再発リスクがあがります。
当院では、アキレス腱炎を「ふくらはぎの問題」としてではなく、「全身の連鎖の中で最後に悲鳴をあげた部位」として捉え、総合的にコンディショニングを行います
まとめ
アキレス腱炎は局所のトラブルとして現れますが、その根底には「下肢全体の連動性の崩れ」があります。
膝や股関節、骨盤の動きが硬くなると、足首にかかる負担が増し、結果的にアキレス腱が代償的に酷使されます。
アキレス腱炎の治療と予防の鍵は、「腱を守る動作パターンを身につけること」です。
炎症が起きるほど頑張っているのはアキレス腱だけではなく、身体全体の使い方のバランスが崩れているサインでもあります。
ランニングも日常動作も、全身が調和してこそスムーズに行えます。
局所のケアに加えて、全身の動きとリズムを整えることが、再発予防とパフォーマンス向上への最短ルートです。

Author:行方悟郎 Goro NAMEKATA
私は中学1年生から陸上競技を始め、大学4年生の卒業まで10年間の陸上競技生活をおくりました。 当時から様々なケガをしてしまい、箱根駅伝出場を目指していた大学3年の秋には坐骨神経痛(梨状筋症候群)を発症しました。
当時のスポーツ整形の医師からは「完治は難しいかも」と言われていましたが、どうしても復帰したいたい一心で手術を受けました。 手術その後のリハビリ、トレーニングを続け、復帰はしたのですが、結果的に最後まで痛みや違和感はなくなりませんでした。
同じように多くの人が ケガが治ったと思って走ったら、また痛くなった、怖くて長く走れない、走って良いのかわからない。自分のケガ(身体)には何が必要なのかわからない、走ってもすぐ疲れてしまう、思うように走れない。という状況に少なからずなっていると感じます。
私は「いつか上記の経験(失敗)や想いを仕事に活かしたい」と考え、はり師、きゅう師などの資格を取得しました。また様々な現場(部活動、大会帯同、接骨院、病院、フィットネスクラブなど)でこれらのことを実践してまいりました。 そして「本当に自分が伝えたい、提供したい治療やスタイル」を突き詰めた結果、現在のスタイル(リライズ鍼灸院)になりました。
◆鍼灸師
◆(公)日本陸上競技連盟B級トレーナー
◆ピラティスリーダーシップコンセプトマットⅠⅡ修了
◆認定心理士
◆習志野高-流通経済大学-トライデント医療看護専門学校
PB/Half1:22:48 Full2:59:37
飛騨高山ウルトラマラソン100㎞完走8回
チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン120㎞完走