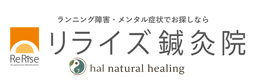「朝起きがけに強く痛みがでる」
「長い距離を走り終わった後は痛むが次の日には痛みが取れた。」
「当初は足を着くだけでも痛みがでた。」
症状は様々です。
当院でも複数の方を治療をしていますが、慢性化、長期化すると厄介な障害です。
トレーニングをしていなくても立っているだけで負荷がかかる場所ですからね。
それだけに敏感になってきてしまい、ランニングを再開しても着地が怖いという方も多いです。「怖いまま」走り続けると他の場所に影響がでることも多いです。
病態とメカニズムの理解
足底腱膜炎は、足底腱膜(plantar fascia)が踵骨(calcaneus)に付着する部位に過度な牽引ストレス(traction stress)が繰り返し加わることで、微細損傷・炎症・線維化が生じる病態です。
足底腱膜は踵骨から足趾の基部にかけて扇状に広がる強靭な結合組織で、
歩行・ランニング時にはアーチのバネ構造(ウィンドラス機構)として衝撃を吸収・推進力へ変換する重要な役割を担っています。

ところが、以下のような状態ではこの機構に破綻が生じます。
下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)の短縮・過緊張
→ アキレス腱を介して踵骨を強く牽引し、足底腱膜の張力が増大。
足趾群の機能低下
→ 地面を掴む動作が減り、足底腱膜が常に受動的に引き伸ばされる。
過回内(オーバープロネーション)や扁平足傾向
→ アーチの低下により腱膜が持続的に伸張される。
つまり、足底腱膜炎は単なる「足裏の炎症」ではなく、
下腿三頭筋 → 踵骨 → 足底腱膜 → 足趾群という連動チェーンの不均衡が生み出す“牽引ストレス連鎖”の結果ともいえます。
足底腱膜炎のコンディショニング
足底腱膜炎の改善・再発予防には、炎症の鎮静 → 筋膜ラインの再調整 → 機能的再教育というステップが有効です。
1. 急性期(炎症コントロール)
-
安静、患部外トレーニング・軽度の足底マッサージ(ゴルフボール転がしなど)
-
超音波による血流改善による組織の早期治癒
2. 回復期(下腿三頭筋と足底のリリース)
-
ヒラメ筋・腓腹筋のストレッチ
→ 壁押しストレッチを膝伸展・屈曲の両方で行う。 -
足底筋膜のリリース
→ フォームローラーやボールでアーチ沿いを圧迫・転がす。 -
アキレス腱―踵骨―足底腱膜の連続性を意識して、
膝下全体の「張り」を整えるイメージで行う。
3. 機能回復期(足趾群の活性化と荷重ライン修正)
-
タオルギャザー(足指でタオルをたぐり寄せる)
-
トゥスプレッド(足趾を広げる)
-
片脚立ちでアーチ保持(母趾球・小趾球・踵の3点支持)
-
ランニング時には、足趾の推進感覚を意識し、
地面反力を足底全体で受け止めるような接地へと導く。
4. ランニングフォームの再教育
-
膝下の過度な伸展・ヒールストライク(踵着地)の修正
-
アーチをつぶさず、前足部で柔らかく受ける”を意識することで、
足底腱膜の牽引負担を軽減できる。
まとめ
足底腱膜炎は「足裏の炎症」ではなく、
下腿三頭筋―踵骨―足趾群の連動不全による牽引ストレス障害として理解することが重要です。
コンディショニングの鍵は、
① 下腿の柔軟性を取り戻すこと、
② 足趾の能動的な働きを再構築すること、
③ 正しい荷重ラインで走る身体感覚を取り戻すこと。
この3点が整うことで、再発しにくい足づくりと、
地面と対話するような“しなやかなランニング”が可能になります。

Author:行方悟郎 Goro NAMEKATA
私は中学1年生から陸上競技を始め、大学4年生の卒業まで10年間の陸上競技生活をおくりました。 当時から様々なケガをしてしまい、箱根駅伝出場を目指していた大学3年の秋には坐骨神経痛(梨状筋症候群)を発症しました。
当時のスポーツ整形の医師からは「完治は難しいかも」と言われていましたが、どうしても復帰したいたい一心で手術を受けました。 手術その後のリハビリ、トレーニングを続け、復帰はしたのですが、結果的に最後まで痛みや違和感はなくなりませんでした。
同じように多くの人が ケガが治ったと思って走ったら、また痛くなった、怖くて長く走れない、走って良いのかわからない。自分のケガ(身体)には何が必要なのかわからない、走ってもすぐ疲れてしまう、思うように走れない。という状況に少なからずなっていると感じます。
私は「いつか上記の経験(失敗)や想いを仕事に活かしたい」と考え、はり師、きゅう師などの資格を取得しました。また様々な現場(部活動、大会帯同、接骨院、病院、フィットネスクラブなど)でこれらのことを実践してまいりました。 そして「本当に自分が伝えたい、提供したい治療やスタイル」を突き詰めた結果、現在のスタイル(リライズ鍼灸院)になりました。
◆鍼灸師
◆(公)日本陸上競技連盟B級トレーナー
◆ピラティスリーダーシップコンセプトマットⅠⅡ修了
◆認定心理士
◆習志野高-流通経済大学-トライデント医療看護専門学校
PB/Half1:22:48 Full2:59:37
飛騨高山ウルトラマラソン100㎞完走8回
チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン120㎞完走