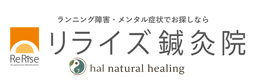ランニングやダッシュ、ジャンプ動作の中で突然「プツッ」と筋に痛みを感じ、走行を中断せざるを得なくなる――これが代表的な「肉離れ(筋損傷)」です。
特に発生しやすいのは ハムストリングス(大腿後面) と 下腿三頭筋(ふくらはぎ)。いずれもランニング動作において強く伸ばされながら収縮する場面が多く、筋線維に大きなストレスがかかるためです。
本稿では、これらの部位に共通する病態の理解と、再発予防を含めたコンディショニングの考え方を整理します。
病態とメカニズムの理解
肉離れは、筋線維が急激な伸張ストレスに耐えきれず損傷する現象です。
特に重要なのは、「筋の収縮様式」と「損傷部位」の理解です。
1. 筋の収縮様式と損傷発生
筋は大きく3つの様式で働きます。
・ 求心性収縮(コンセントリック):筋が短縮しながら力を発揮する
・ 遠心性収縮(エキセントリック):筋が伸ばされながら力を発揮する
・ 等尺性収縮(アイソメトリック):長さを変えずに力を維持する
肉離れの多くは、このうち 遠心性収縮 時に多く発生します。
例えば、裏腿・ハムストリングスでは、走行中の スイング後期〜接地前 に股関節が屈曲し膝が伸展される際、強い遠心性負荷がかかります。
下腿三頭筋では、蹴り出し動作や着地時 に足関節が背屈方向に引き伸ばされながら収縮するため、筋線維が引き裂かれるようなストレスを受けます。
2. 損傷部位の特徴
損傷は、筋腹部 そのものよりも、筋腱移行部(myotendinous junction) に多く見られます。
この部位は、筋線維と腱の構造的性質が異なり、ストレス集中が生じやすい「構造的弱点」です。
急激な遠心性負荷が加わると、この接合部で微細な断裂や炎症が生じ、典型的な肉離れの病態を呈します。
陸上競技においては基本的に短距離に多いのですが、当院では中高年ではマラソン愛好者でも事例が多くあります。おそらく加齢に伴なう金組織の劣化が多くの要因と思われます。
さて場所肉離れを一度受傷してしまうと基本的に受傷前と全く同じ状態にはなりません。
かならず瘢痕(傷跡~かさぶたの傷様)が残ります。その部位を中心に硬くなったり、動きが悪くなり、上記の硬さや違和感に繋がっていることもあります。
したがって最終的には重心の取り方など見て、患部に負担をかけにくい動き、フォームづくりを
行っているお客様も多数おります。最初からその視点で対応したほうが良い場合もあります。
肉離れのコンディショニング
肉離れのコンディショニングは、修復 → 再建 → 再発予防 の3段階で考えることが重要です。
全般にわたって過度な伸長ストレッチは禁忌ではありますが、筋繊維の再構築を破壊しない程度のストレッチは早い段階で行うことで、受傷部の癒着や短縮を防ぐことにもなり、結果的に早い復帰にもつながります。
1. 修復期(急性期)
-
炎症・腫脹・治癒増進のコントロール(超音波、低周波、鍼灸など)
-
過度な伸張やマッサージを避ける
-
痛みの軽減と血流改善を目的に、周辺筋の軽度収縮運動や呼吸性リズムを導入
2. 再建期(亜急性期)
-
痛みの範囲内での等尺性収縮トレーニングから開始
-
徐々に遠心性負荷トレーニングへ移行(例:ノルディックハム、カーフロワーダウン)
-
筋膜リリース・ストレッチにより、筋腱移行部の滑走性を回復
3. 再発予防期(復帰期)
-
筋出力・柔軟性・協調性を総合的に評価
-
左右差の是正(筋力バランス・骨盤アライメント)
-
ランニングフォームの改善:ストライド過大や接地衝撃の強さはリスク要因
-
再発リスクの主因:組織修復不十分のまま競技復帰
→ MRIなどで瘢痕組織が残ると、再発率は20〜30%に上るとの報告もあります。
4. 予防的エクササイズ例
-
ハムストリングス:ブリッジ系トレーニング
-
下腿三頭筋:カーフレイズ+遠心性コントロール、アンクルモビリティ改善
-
補助:股関節伸展・足関節底屈の協調運動を意識した動作トレーニング
リハビリ・コンディショニング過程のおいても再受傷のリスク管理(段階的負荷)などに考慮することが必要です。
まとめ
肉離れは、筋の強い遠心性負荷と筋腱移行部のストレス集中が主な発生機序です。
ハムストリングス・下腿三頭筋いずれもランニングの推進力を担う重要な筋群であり、損傷後の回復過程では「筋の再生と動作パターンの再教育」が不可欠です。
再発を防ぐためには、筋力と柔軟性の回復だけでなく、ランニング動作全体の調整(姿勢・接地・リズム) までを含めた包括的なコンディショニングが求められます。

Author:行方悟郎 Goro NAMEKATA
私は中学1年生から陸上競技を始め、大学4年生の卒業まで10年間の陸上競技生活をおくりました。 当時から様々なケガをしてしまい、箱根駅伝出場を目指していた大学3年の秋には坐骨神経痛(梨状筋症候群)を発症しました。
当時のスポーツ整形の医師からは「完治は難しいかも」と言われていましたが、どうしても復帰したいたい一心で手術を受けました。 手術その後のリハビリ、トレーニングを続け、復帰はしたのですが、結果的に最後まで痛みや違和感はなくなりませんでした。
同じように多くの人が ケガが治ったと思って走ったら、また痛くなった、怖くて長く走れない、走って良いのかわからない。自分のケガ(身体)には何が必要なのかわからない、走ってもすぐ疲れてしまう、思うように走れない。という状況に少なからずなっていると感じます。
私は「いつか上記の経験(失敗)や想いを仕事に活かしたい」と考え、はり師、きゅう師などの資格を取得しました。また様々な現場(部活動、大会帯同、接骨院、病院、フィットネスクラブなど)でこれらのことを実践してまいりました。 そして「本当に自分が伝えたい、提供したい治療やスタイル」を突き詰めた結果、現在のスタイル(リライズ鍼灸院)になりました。
◆鍼灸師
◆(公)日本陸上競技連盟B級トレーナー
◆ピラティスリーダーシップコンセプトマットⅠⅡ修了
◆認定心理士
◆習志野高-流通経済大学-トライデント医療看護専門学校
PB/Half1:22:48 Full2:59:37
飛騨高山ウルトラマラソン100㎞完走8回
チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン120㎞完走