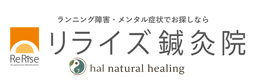刺激依存型と認知制御型の集中——感覚の違いの正体とは?
「また、やってしまった。今日もスマホでyoutubeに集中し過ぎて、やるべき仕事ができなかった・・・」
こんなことありますよね。
集中という言葉には、一見シンプルで誰もが理解できるイメージがあります。しかし実際には、その「型」や「質」は大きく異なります。
集中について考えてみますと以下の整理になります。
-
刺激依存型の集中(受動的没頭)
-
認知制御型の集中(能動的没頭)
-
その感覚的な違いの正体
刺激依存型の集中(受動的没頭)
これは外部からの刺激に引き込まれる形の集中です。代表的なのは、映画やゲーム、スマートフォンのSNSのスクロール、動画サイト閲覧時の脈絡のない、終わりのない延々としたダラダラとした視聴。
-
特徴
-
強い感覚刺激(映像、音響、報酬系のフィードバック)がトリガー
-
ドーパミン分泌に依存
-
「気づいたら時間が経っていた」という没頭感
-
認知的努力は少ない
-
やめる時に「中断困難感」が強い
-
新しい投稿・動画=予測できない報酬(ドーパミンが最も出やすい条件)
-
「次はもっと面白いかも」という期待が強化され、スクロールや連続再生を止めにくい
-
脳科学的には、側坐核や線条体を中心とした報酬系の活性化に支えられており、受動的なトランス状態に近いとも言えます。
☆注意のモード
・外部刺激に「受動的に引きつけられる注意」
・前頭前野の努力はあまり必要なく、自動で注意が釘付けになる。
☆疲労感が少ない理由
・自発的な努力が少なく、報酬系が常に小さな「快」を与えてくれるため。
・深い記憶定着や理解は伴いにくい(海馬の働きが浅い)
・「集中」というよりは「報酬駆動による没頭」に近い。
認知制御型の集中(能動的没頭)
一方でこちらは、外的刺激に左右されず、自らの意思で注意をコントロールする集中です。
勉強や研究、楽器の練習、瞑想やスポーツの「ゾーン体験」などが代表例。
-
特徴
-
内的な目標や意図に基づいて注意を配分
-
前頭前野(特に背外側前頭前野)の関与
-
「努力している感」と「やがてスムーズに流れる感」が共存
-
中断は比較的しやすい
-
終了後に「やりきった満足感」が残る
-
☆勉強・読書
・前頭前野(PFC)が主役
・注意の維持、雑念の抑制、理解の構築を行う。
・外部から強い刺激がなく「退屈」になりやすいため、自分で注意を制御する力が必要。
☆報酬系の働き方
・即時的なドーパミンは少ない。
・「理解できた!」「ひらめいた!」という達成の瞬間に強く出る(遅延報酬)。
☆疲労感が強い理由
・PFCは脳の中で特にエネルギー消費が大きく、持続力も弱い。
・そのため「頑張っている感じ」が伴う。
感覚的な違いの正体
両者を経験的に比べると、次のような「感覚の質の違い」が浮かび上がります。
-
身体感覚
-
刺激依存型:姿勢や呼吸への意識が希薄。「身体を忘れる」
-
認知制御型:体幹や呼吸リズムと調和。「身体が伴走する」
-
-
時間感覚
-
刺激依存型:「時間を奪われた」感
-
認知制御型:「時間を生み出した」感
-
-
終了後の余韻
-
刺激依存型:だるさ、虚脱感、もう一度刺激が欲しくなる
-
認知制御型:充足感、疲労はあっても快い
-
言い換えれば、前者は外部に「連れ去られる」感覚、後者は内側から「自ら操縦している」感覚が核心的な違いです。
まとめ
-
刺激依存型の集中は「報酬系ドーパミン回路による受動的没頭」
-
認知制御型の集中は「前頭前野による能動的制御」
-
感覚的な違いの正体は、「身体意識・時間意識・終了後の余韻」の質に現れる
日常生活では両方の集中を使い分けることが自然ですが、自己成長や学習、心身の調律には 認知制御型の集中を意図的に育てることが重要だといえるでしょう。
スティーブジョブズは自分のこどもに14歳までスマートフォン・タブレットを持たせなかったという有名な話があります。やや乱暴な言い方をすれば刺激依存型集中の震源地であるスマートフォンがいかに脳に悪影響があるか、留意していたのでしょう。
スマートフォンも認知制御型の使い方をすれば素晴らしいツールであることは間違いないと思いますが、今日のSNS界隈を鑑みるに自身もふくめほとんどの人が刺激依存型の集中であるのではないでしょうか。
人は強くない、目の前の短絡的な「快」や過去の「苦い記憶」に惑わされます。しかし、一方では認知の力をつかって生産的な活動もできるはずです。
|
参考文献 |

Author:行方悟郎 Goro NAMEKATA
当院には、自律神経の乱れ、抑うつ、パニック、不安、不眠、慢性的な疲労感、頭痛、首の痛みなど――
心と身体のバランスを崩し、仕事や学校を休みがちになったり、何とか日常を続けながらも、長いあいだ不調を抱えている方が多く来院されています。
では、その「不調の原因」とは何でしょうか?ストレスでしょうか?仕事、家庭、人間関係…あるいは姿勢や生活習慣、慢性的な疲労や過緊張…? ――答えは一つのようで、一つではありません。
ご自身で「わかっている」と感じるときもあれば、「何が原因かわからないけれど、ただしんどい」ということも自然なことです。
当院では、鍼灸・整体施術、心理カウンセリング、ピラティスなどを通して、身体との対話、心との対話、そして人との対話を大切にしながら、少しずつ「本来の自分」に立ち返るお手伝いをしています。
私たちが信じていること――それは、身体は本来“治りたがっている”存在であるということ。
自然のリズムと心身の声に耳を傾け、あなた自身の内に眠る“治る力”を、ここで一緒に呼び覚ましていきましょう。

鍼灸師・認定心理士・ピラティスインストラクターとして、身体・心・自然の調和を探求し続けています。2013年より当地にて鍼灸院を開業。自律神経の不調やアスリートの身体ケアに携わる中で、対話と身体感覚の重要性を実感し、心理学やピラティスも統合。
現在はポリヴェーガル理論を軸にした施術と、「動く瞑想」としてのワンネスピラティスを実践中。すべての人が“自らの治癒力”に気づき、自分自身とつながる場を提供しています。
■資格等
□鍼灸師
□認定心理士
□介護予防運動指導員
□ピラティスリーダーシップコンセプトマットⅠⅡ修了
□(公)日本陸上競技連盟B級トレーナー
□医薬品登録販売者(未登録)